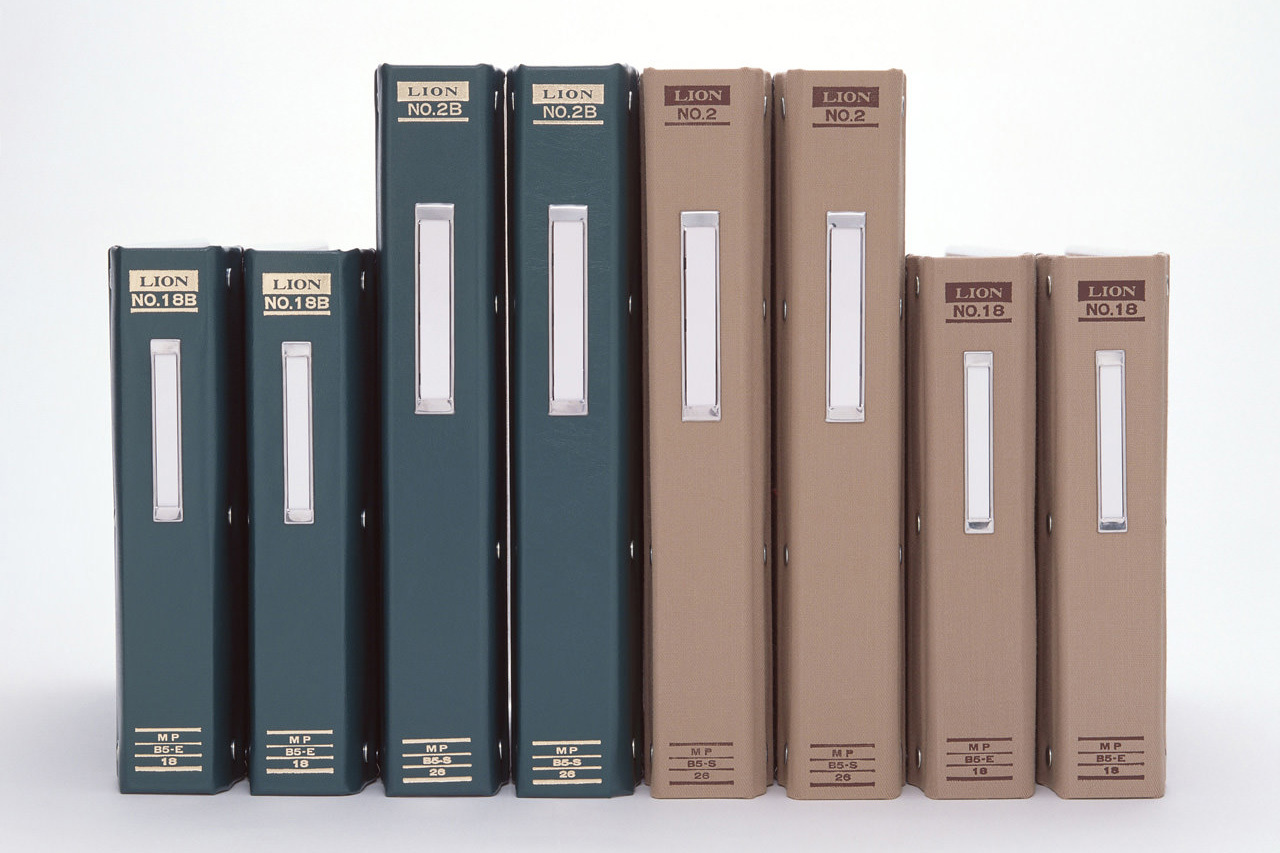こちらでは巷に言う、「節税」について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
創業間もない社長から、「先生、税金対策はどうすればいいんですか?」と言う質問を忘れたころに頂戴致します。当然ではありますが、税金は、利益に対してかかるものですので、税金対策の前提として、事業から利益を生み出さないと、税金対策など必要がありません。利益を出すためには、売上を増やさないといけませんし、業務の効率化、無駄の排除により、経費を削減しなければなりません。経済環境が益々厳しさを増す中、創業間もない方にはこれが中々大変なことなのです。
私はお客様である経営者に、こう言うようにしています。「税金対策は税理士の仕事です。まずは、しっかりと事業計画を立てて、実績を少しでも計画に近づけるようにして下さい。税金を負担出来るようになれば、立派な経営者としての第一歩を踏み出したことになりますから」
とは言え、税金対策は事業経営にとってとても大切なことであることは間違いがありません。幾つか基本的な節税対策を下記に記載しましたので、ご参考になさってください。
法人か個人事業主か?
節税のお話をする前に、起業する上で、最初に考えておいた方が良いと思われることは、会社の形態を法人とするか、個人事業主とするかという点だと思います。
大した違いはないかと考えがちですが、起業間もない経営者にとっては、どちらを選択するかによって、社会保険料や税金の負担等、直接、会社の利益や資金繰りに影響を与えるため、慎重に検討する必要があります。
特に、創業間もない会社にとって、資金繰りの見通しを誤ることは、会社の存続にとって、致命的となりかねません。起業間もない時期は、会社の資金繰りは、最も経営者が重視すべき事項となりますので、この点では、しっかりと考えておく必要があると思います。
そのためにはまず、会社の事業計画では、会計上の利益と資金繰りを明確に区別して、それぞれ、会社設立前から十分に検討する必要があると思います。
では、簡単ではありますが、法人と個人の選択の違いによって、会社経営で差異が生じる場合をご紹介しましょう。
Aさんは、ある会社を法人として立ち上げ、創業当初の事業計画から、役員報酬を月30万円としました。ここで、話を分かりやすくするため、社員はおらず、社長一人の会社とします。法人の場合、基本的に役員報酬は、社会的な一般常識の範囲内であれば自由に社長個人が決めることが出来ます。無報酬でも大丈夫ですが、役員報酬を支給するのが一般的です。
実際に事業を始めてみると、思ったように売上高が上がらずに、月30万円の役員報酬の手当てにも窮する状態でした。そこで、社長は役員報酬を会社からは受け取らずに、その分を会社の運転資金に回し、自分の生活費は、これまでの貯金を取崩して何とか対応をしていました。
ここまでは、良くあるケースと思いますが、ここで注意して頂く点があります。
役員報酬を30万円と決めた以上、損益計算書上、役員報酬は30万円として計上されますが、その報酬がたとえ社長個人へは未払(従って、社長からも会社からも資金の流失は発生しない)でも、当該報酬に係る住民税(翌年から)及び社会保険料は、個人及び会社負担分とあわせ、役所に定期的に支払わなければなりません。すなわち、報酬は実質的になくても、当該報酬に係る税金や社会保険料等の社外流失は生じてしまうということです。
ちなみに、役員報酬が30万円の場合、社会保険料に係る個人及び会社負担額は、およそ9万円となります。会社負担分と言えども、基本的には、社長自らの負担分と違いはありませんので、(財布は同じということです。)これはかなりの出費になります。この他に住民税(翌年から)を負担しなければならないのです。創業間もない会社にとっては、本当に痛い出費になります。
こうしたことを回避するためには、設立前からの事業計画をしっかりと立てて、役員報酬も、社会保険料や税金に係る個人及び会社負担分が最小になるように適切にシミュレーションをする必要があります。
個人事業主は、こうした事態は回避できます。
もちろんこれだけではありませんが、創業当初は、中々売上高が上がらずに、経費のみが重く会社経営にのしかかり、少しの出費でも抑えたいものです。
従いまして、様々なことを考慮しても私個人の意見と致しましては、起業後、利益が十分に出せる状態になるまでは、個人事業主として行い、利益が十分に出るようになった後に、法人化することがよろしいのではないかと思います。
消費税の負担を考えても、個人+法人で合計4年間免税事業者として消費税の負担を回避出来ます。(※注1)
また、税務署に提出する申告書等の資料も法人よりも個人事業主の方が簡便的な取扱いでありますし、税務調査も法人よりは、その可能性が一般的に低いと言われています。
利益が十分に出るようになった後は、節税対策に関しては、法人化する方が、選択肢は多いと言えますので、十分に利益が出るようになってから、法人化するのでも遅くはないと思います。
もちろん、法人又は個人事業主のそれぞれに長所・短所があり、一概にどちらがいいとは言えないのですが、こうしたことを考慮した上で、個人又は法人の別を決めて頂ければと思います。
| ※注1 |
|---|
インボイスの登録を受ける(適格請求書発行事業者に該当する)場合には、個人・法人問わず、登録時から課税事業者になるため、上記の取扱いを適用できない場合があります。インボイスの登録を受けるか否かは、事業者の主な取引先が消費者なのか事業者なのかによっても変わります。
主な節税方法
役員報酬を利用した節税方法
中小企業にとって、節税対策としてだけではなく、経営全般を考慮しても、役員報酬をどの程度の水準とするかの決定は、極めて重要な判断事項だと思います。
役員報酬は、基本的に、経営者自らの判断で決めることが出来ます。その判断次第では、すなわち、役員報酬の水準次第では、会社の税金額に大きな影響を与えます。また、役員報酬に係る判断は、会社が負担する税金だけではなく、役員報酬に係る経営者自身の所得税等にも影響を与えます。
従いまして、会社設立前から、事業計画をしっかりと立て、この程度の利益水準であれば、会社に係る法人税等と経営者自身の報酬に係る所得税等(社会保険料を含みます)がいくら位生じるのかというシミュレーションをしっかりとした上で、役員報酬を決定出来れば、大きな節税効果を生み出すことが出来ると言えます。
生命保険に加入する
生命保険による節税はその効果が十分に見込める反面、その効果を得るためには、注意点も多くあり、留意が必要です。
生命保険による節税効果の基本的な考え方は、解約返戻金のある生命保険に加入し、当該生命保険の掛け金を損金算入して利益を圧縮し節税効果を得る一方で、一定期間後に当該生命保険を解約してこれまでの掛け金合計額と同額程度の返戻金を受取るというものであります。解約返戻金は、支払った合計額を控除した金額は益金となり、税額が増えてしまいますから、役員退職金等の支払を同時期に行うことにより、その益金を相殺し、実質的な節税効果が得られるようにします。退職金には税務上優遇処置がありますからほとんど税金がかかりません。こうしたやり方が一般的に言われている生命保険による節税方法です。(※注2)
ただ、生命保険を利用した節税には以下の注意点があります。
解約返戻金は、税務上益金となることから、この益金を相殺する費用の発生が同時期に生じることが、節税対策上不可欠となります。役員退職金が主に利用されていますが、こうした出口戦略を当初から検討していなければその効果を得ることは出来ません。
一定期間掛け金の支払を継続しなければ、一定の効果を得ることが出来ません。仮に途中で生命保険を解約せざるを得なくなった場合には、当初想定した節税効果を得ることが出来ないばかりか、大きな損失を被る可能性もあります。掛け金を一定期間継続して支払続けるわけですから、企業活動に利用出来るキャッシュ・フローがその分少なくなってしまいます。有利な投資の機会があったとしてもその制約になるかもしれません。
以上のように生命保険を利用した節税手段にはいくつかの注意点がありますが、一定の節税効果は期待出来ますので、利用しない手はないと思います。
| ※注2 |
|---|
2019年の税制改正により、従来、全額損金計上が可能であった保険商品(全損型定期保険等)について、条件によっては保険料の一部が資産計上されることとなりました。
4年落ちの中古車を購入する
固定資産の取得原価は、会計・税務とも、その固定資産の利用期間にわたって、一定の方法で費用化します。固定資産の利用期間は、その固定資産の使用頻度、性質、メンテナンス状態、自然環境等、様々な要因により個々の企業で異なるものですが、税務上は耐用年数という基準を設けて、その耐用年数で一定の方法で費用化すれば損金として全額認めますという方針を取っています。これは新品も中古品も基本的には同様なのですが、中古品の固定資産に係る耐用年数の算出計算を上手く利用すれば、一定の節税効果が見込めます。
例えば、新車の自動車の耐用年数は6年と税務上決められていますので、取得費用を6年間にわたって一定の方法で費用化しなければ税務上は損金算入出来ないことになりますが、一定期間経過後の中古車を購入した場合、1年間で取得費用の全額を一度に費用化することも可能です(減価償却費は月割りなので、1月に購入した場合は全額損金算入が可能)。
中古車を上手く利用することにより、節税効果を得ることが出来ます。
社宅を利用する
従業員や役員の賃貸住宅を社宅とすることで、当該賃貸住宅に係る家賃を会社の経費で落とすことが可能になります。会社の経費で落とすためには、賃貸住宅等に一定の条件がありますが、この条件を満たせば、家賃の8割から5割程度は会社の経費として費用に落とすことができますので、従業員や役員は、家賃の2割から5割程度の負担をすれば良いことになります。もちろん、この家賃の会社負担分は従業員の給与等にはなりませんので、所得税等が課税される心配はありません。
小規模企業共済に加入する
役員報酬が節税に大きな効果があることはご説明致しました。役員報酬は節税の観点から、一丁目一番地であることは間違いありません。ただ、役員報酬を上げてしまうと会社の利益が減少するため法人税等の負担は軽減しますが、一方で、役員報酬に係る所得税や住民税等の負担はむしろ増してしまいます。そこで、所得税等の負担を増やさず、実質的な役員報酬増加の効果をもたらす手段が、小規模企業共済という、一種の退職金制度です。
毎年の掛け金(最大84万円/年間)が所得から控除されますし、払い戻しに当たる共済金は退職金扱いとなり、退職金と同様の控除が受けられます。退職金は老後の生活保障という意味で、通常の給与所得に課される税金と比較して大きく優遇されています。この制度を利用すれば、ほとんど税金の負担なしで退職金がもらえる(実際には自分で掛け金を負担していますが・・・)ことも可能となる制度なのです。利益の出ている会社にとっては、十分に検討する価値があると思います。
旅費規程を策定する
旅費規程がありますと、出張時に支払う日当が会社側では損金算入出来るにも関わらず、当該日当には所得税や住民税が課税されないため丸々の金額が給与となります。また、消費税の対象ともなるので、かなり有効な節税策となります。
売上の計上基準を工夫する
法人税法では、棚卸資産に係る売上計上日に関しては、その引渡しの日としています。この引渡しとは、棚卸資産を会社が出荷した日、お客さんが棚卸資産を受取った日、棚卸資産がと契約書通りに機能するのか検証した日等々、いくつかの基準があり、会社は自由に決めること出来ます。ただ、一旦決めた基準は合理的な理由がない限り、継続して適用しなければなりません。
この売上計上基準をもっとも遅いものにすれば、その分、利益を少なくする効果があるため、節税効果があると言えます。合理的理由があれば、売上計上基準の変更も認められます。売上計上基準の変更により節税効果を見込める場合もあります。
また、売上計上基準は会社にひとつしか認められないというわけではありません。実態に応じた売上に係る複数基準の採用も節税効果を生む可能があります。
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら